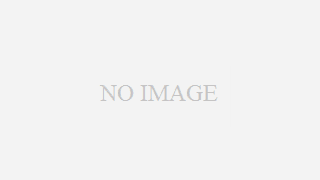 ダイジェスト
ダイジェスト 「日本文化の特徴は…」。主語が大きい文化論を語ることの「落とし穴」
日本語は文字が多いから難しい?
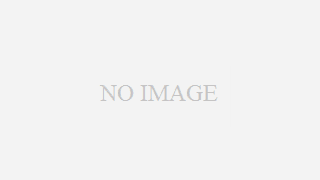 ダイジェスト
ダイジェスト 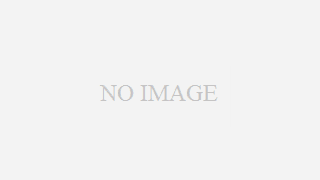 ダイジェスト
ダイジェスト 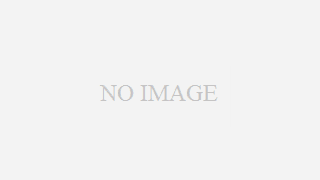 ダイジェスト
ダイジェスト 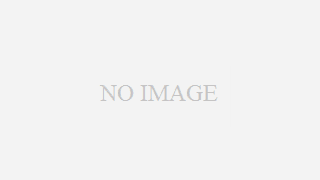 ダイジェスト
ダイジェスト 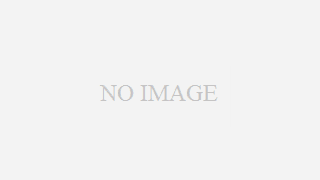 ダイジェスト
ダイジェスト 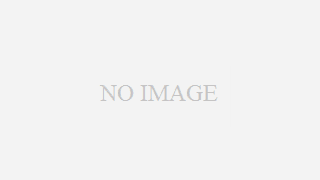 ダイジェスト
ダイジェスト 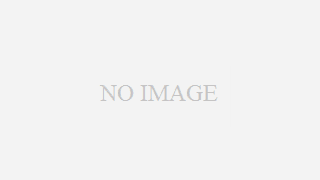 ダイジェスト
ダイジェスト 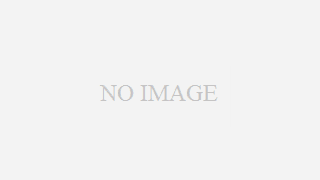 ダイジェスト
ダイジェスト 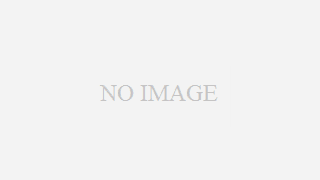 ダイジェスト
ダイジェスト 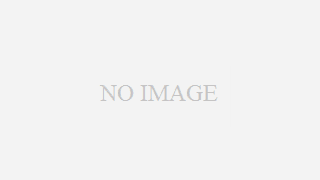 ダイジェスト
ダイジェスト